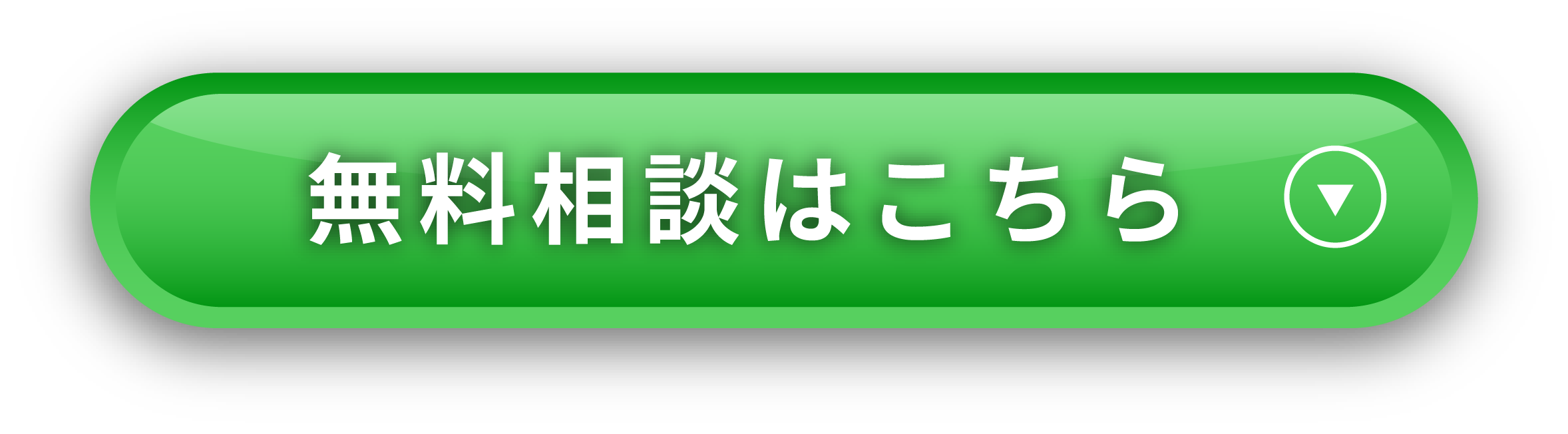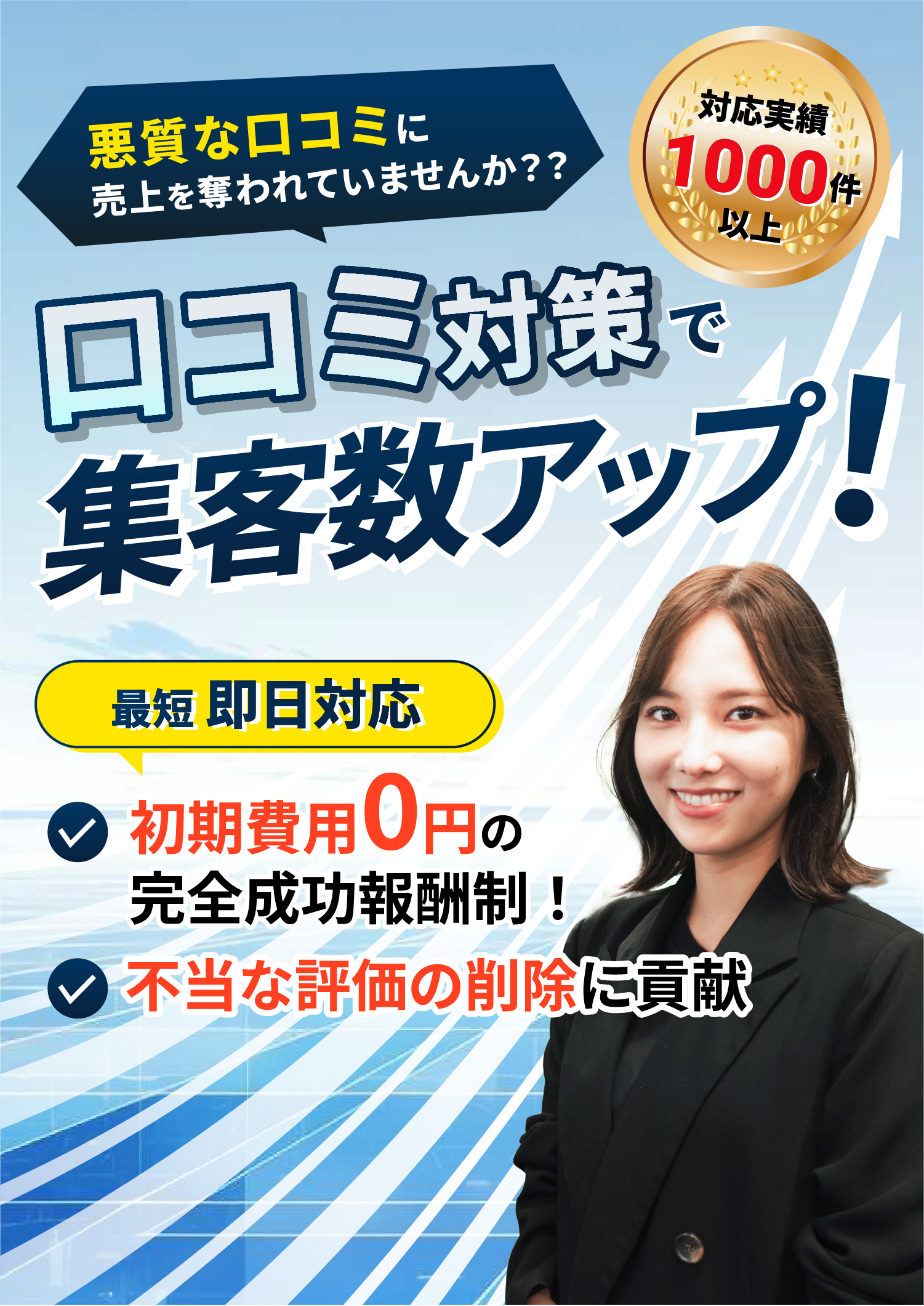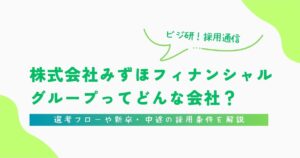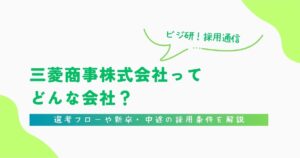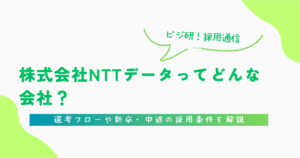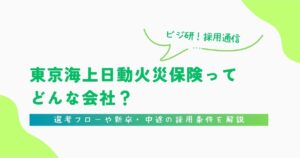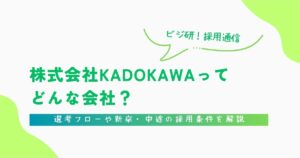学歴フィルターって本当にあるの?学歴フィルターを乗り越えて内定を掴み取るには【2025年度版】
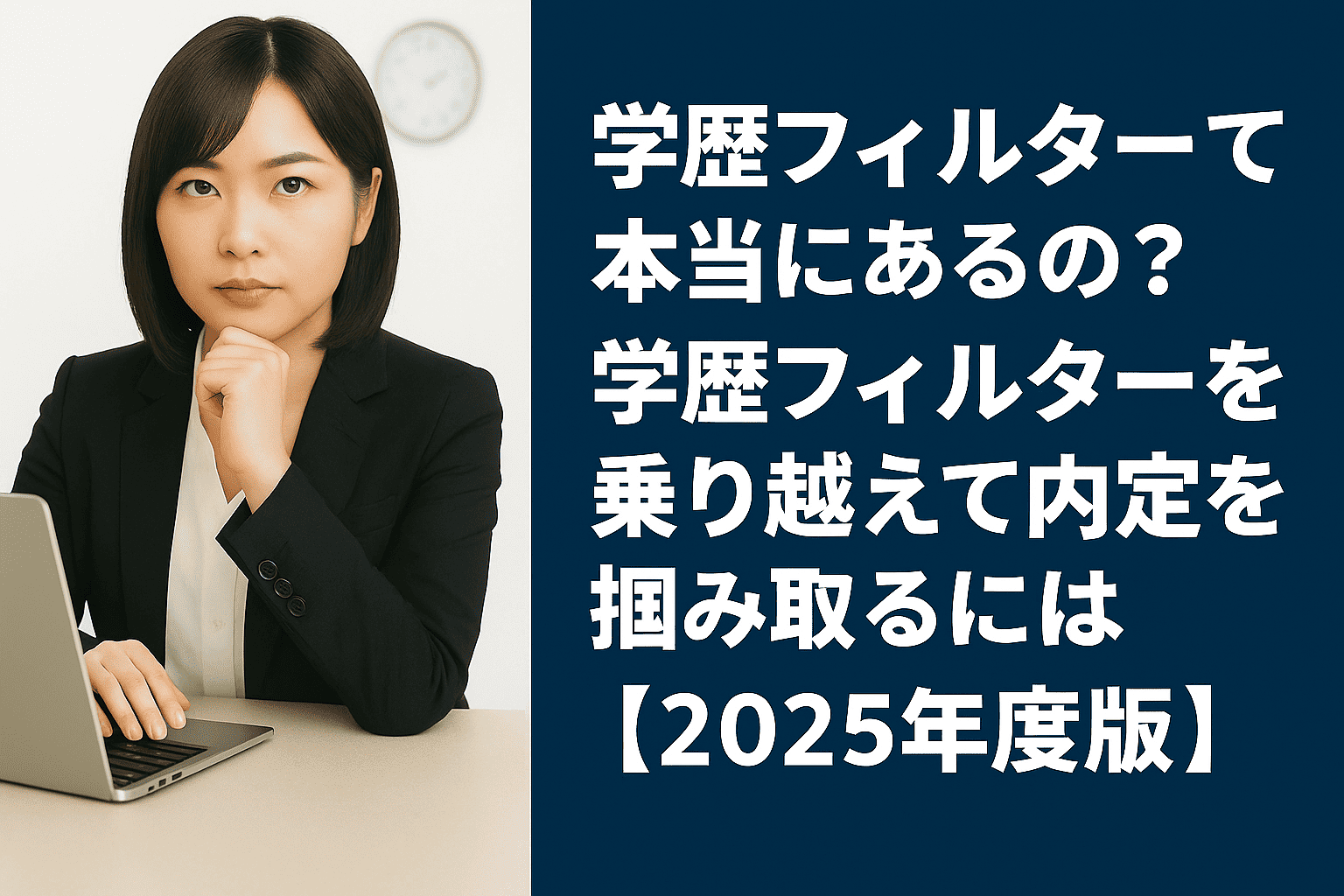


今回は、新卒就活でよく耳にする「学歴フィルター」についてまとめました。
学歴フィルターといってもボーダーはどれくらいなのか、学歴フィルターを乗り越えて内定を掴み取るにはどうしたらいいのか悩んでいる方は多いかと思います。
本記事では、そのような悩みを持つ就活生に向けて、実際に新卒採用において学歴フィルターは存在するのか、存在するとしたらどのように対策していけばいいのかについて解説しています。
本記事を読んで、志望する企業への内定獲得に向けた選考対策のご参考にしていただけたら幸いです。
学歴フィルター

近年、SNSの発達により就職活動の際にSNSで情報収集する方が増えてきています。
そんな中、度々話題になるのが「学歴フィルター」についてです。
「〇〇会社に学歴フィルターで落とされた」「学歴ってどこまで重視されるの」など、就活生の様々な不安や不満の声があがっています。
では、そもそも学歴フィルターとはどのような定義なのか、下記でご紹介いたします。
学歴フィルターとは
学歴フィルターとは、企業が採用活動を行う際に、その採用活動を効率化するために選考の初期段階において、応募者の出身大学に基づいて選考を行うことを指します。
つまり、企業によって「この大学以下は基本的にお見送り」もしくは「この大学以上の応募者は優遇選考して、それ以下は通常選考を行う」という一定の学歴のボーダーラインを設けることにより、選考過程を簡潔化・差別化する施策です。
ほとんどの企業が公には学歴フィルターの存在を認めていませんが、実際には採用に力を入れたい大学リストを作成し、内部で選考の優遇可否について学歴を判断基準の一つとして取り扱っている場合があります。
学歴フィルターを設けることが違法かどうかは、様々な意見が飛び交い明確に違法と断言できません。しかし、世間一般に差別しているという印象を持たれるため、企業は学歴フィルターの存在について否定的な態度を示していると考えられます。
学歴フィルターによる就活生への影響
学歴フィルターの存在を公表する企業がほとんど見られないものの、実際のところどれだけの企業が学歴フィルターを設けているのか、気になる就活生の方は多いと思います。
就活生側としても、学歴フィルターを設けていないと公言しつつ、学歴で選考を落とされたんじゃないか?と感じる場面があるのではないでしょうか。
以下で学歴フィルターが就活生に与える影響について、解説していきます。
以下のような場面に自分が出くわした時、その企業は学歴フィルターを設けていると推察することができるかもしれません。
エントリーシート(ES)が通過しにくい
一緒に就活を進める同期や部活・サークルの先輩達に何度も添削をしてもらって完成した自信満々のエントリーシート(ES)が、あっさりと落とされてしまう、といった経験をお持ちの方は少なくないと思います。
「自信作のESが通過しなかった」場合が全て学歴フィルターの影響とは断定できませんが、企業側があなたの学歴を大きな判断材料として通過の可否を決定した可能性は十分にあり得ます。
もちろん全ての企業に該当するわけではありませんが、既定の水準に達していない学校出身の就活生は、エントリーシートの内容をほとんど読まずに落とされるといった場合もあるのかもしれません。
また、逆に有名大学出身の学生が、「ひどいエントリーシートを提出したのに選考通過できた」という実例も多く挙げられているため、「高学歴を優遇する」ための学歴フィルターは実在する可能性は高いと考えられます。
「高学歴向け就活イベント」に参加できない
就活をしていると、様々なイベントに行く機会が多いかと思います。就活支援団体が主催する合同説明会や就活セミナー、企業が個人開催する自社説明会やインターンなどその種類は様々です。
このような就活イベントに参加するにあたっても、学歴が影響することは多々あります。
具体的には、企業が主催する自社説明会について、東京一工や地方旧帝大、早慶やMARCHといったいわゆる高学歴層の学生には案内を送るが、世間一般的に高学歴とは認知されていない大学出身の学生に対しては案内を送らないといったケースがあります。
上記では自社説明会を挙げましたが、それ以外の合同説明会やセミナーに関しても「高学歴向け」といった条件付きの就活イベントは数多く存在します。
これらの就活イベントの存在によって、就職活動における情報格差が高学歴層とそうでない層とで生じてしまう原因につながっていると考えられます。
選考が進んでもリクルーターがつかない
上記で、学歴フィルターによってエントリーシートが通過しづらくなる点について紹介しましたが、書類選考を通過しても学歴フィルターの影響を受ける可能性があります。
多くの企業では、選考が進むと応募者である学生に対して選考をフォローアップしていくリクルーターがつきます。その理由として、学生のキャリアに対する考え方と自社の事業内容や制度・社内文化がマッチしているかを見極めることに加え、入社が期待できる学生に対して自社の魅力を発信し続け、さらに志望度を上げてもらうといった狙いもあります。
中には、選考が進んでもリクルーターがつかない企業も存在するため、リクルーターがつかなかったからといって学歴フィルターにかけられてると断定はできませんが、他の就活生と自分とで扱いに差が出ていないか、見極める必要があります。
また、その他にも、面接時に深掘り質問をあまりされなかったり、あからさまに横柄な態度を取られるといった可能性も存在します。
選考が進んでも学歴フィルターの影響は存在する可能性はありますが、上記に述べたような対応をされても「学歴フィルターにかけられてどうせ落とされるんだ。」と気落ちするのではなく、「まだ自分の魅力に企業が理解できていないのか!」とポジティブに捉え、自己アピールのやり方を変えたり、受けている企業についてさらに調べ上げて志望度の高さをアピールすることで、自ずと企業側の対応も変わってくる可能性は多いにあります。
選考においては、「学歴はあくまで判断基準の一つでしかない」と自分に言い聞かせて、できることから進めていきましょう。
以降のコラムで、学歴フィルターを乗り越えるための施策もご紹介いたしますので、併せて読んでいただけると幸いです。
行きたい企業のOB/OGが見つからない
就活において情報収集はとても大事な活動です。中でも、行きたい企業のOB/OG訪問をすることで、実際にその企業で働いている社員からリアルな話を聞くことができ、自分が本当にその企業に行きたいのか、入社したら具体的にどのようなキャリアを形成していきたいのかなど、様々な選考対策に使用可能な情報を得ることができます。
企業が学歴フィルターを設けている場合、その企業には特定の大学出身者で占められており、大学のキャリアセンターを使った同大学出身者のOB/OG訪問が難しくなります。
また、運良く自分と同じ大学の出身者を見つけられたとしても、その人に訪問依頼が殺到するため、時間を多く取れない、最悪の場合は訪問すらできないといった場合もあります。
企業が学歴フィルターを取り入れる理由

ここまで、学歴フィルターについての基本的な認識と、就活生への影響について解説してきました。
では、企業はなぜ学歴フィルターを設けるのか、学歴フィルターを設けることで企業が得られるメリットとはなんなのでしょうか?
そういった疑問に対して下記で詳しく解説します。
ぜひ読んでいただき企業側の目線に立って考えてみましょう。
1. 採用コストを抑えるため
まず、大前提として企業は「可能であれば全ての学生に対してじっくり適性を判断し、選考を進めていきたい」という気持ちを持っています。
しかし、人気の企業であれば毎年何千人規模の就活生を相手にする必要があり、全ての応募者に対して書類選考から面接、リクルーターとしての対応を行うとなると多大な時間と人員、費用がかかってしまいます。
また、近年はインターネット関連の発達により、企業へのエントリーにかかる時間や労力が減ってきているため、どんな学生でも簡単にエントリーできるようになってきています。そのため、企業単位あたりのエントリー数が増加し、学歴フィルターを用いざるを得ない企業が多発していると考えられます。
したがって、大手企業や就活生に人気のある企業にとって学歴フィルターは、採用にかかる時間・人員・費用を削減できるシステムなのです。
具体例として、書類選考で特定の基準を満たす大学出身者は問答無用に選考を通過させ、基準に満たない学生のエントリーシートのみを閲覧すれば、大きな時間の節約になります。
また、高学歴向けイベントを実施することで、他のイベントとほとんど同じコストで自社の狙うターゲット層を獲得できるため、得られる利益がより大きい上、非常にコストパフォーマンスが高くなってきます。
2. 基礎的な能力を担保するため
企業の採用担当は低コストで優秀な学生を獲得し、自社に入社してもらうことを第一の目標としています。
そのため、上記で述べたように採用にかかるコストはなるべく削減していく必要がある上、選考を進める学生が優秀であるということを担保しなければなりません。
学歴や偏差値は一概にその人の能力全てを示すものではありませんが、「競争率の高い難関学校に入学する」という目標を立てて、長期に渡り勉強という努力をし、合格という目に見える成果を得ることができたという事実をいわゆる高学歴の学生は持っています。
学校推薦やスポーツ推薦で入学した学生に関しても、推薦を得るために日々勉強や部活に熱心に取り組み、決して低くはない一定の基準を超えることができたため入学することができたという実績を持っています。
そういった学生たちは企業に入社してからも、新入社員として自分の力量を把握し、実現可能な範囲で段階的な目標を立て、成果を上げていくことできる可能性が高いと採用担当側が判断するのも必然ではないでしょうか。
このような理由で、企業側は学歴フィルターを設けることで、低コストで選考を進められる上、一定の能力があると確信できる学生を選択できるのです。
3. ブランド力を維持するため
企業は主にクライアントへ自社の商材を売ることにより利益を得ています。
この時、クライアント側はその企業や担当者が本当に信頼できるのか、安心して取引を行うことができるのか、本当に価値のある商材なのか、などといった不安や疑念を持ちます。自分たちが頑張って得たお金を払うわけですから、当然相手を信用できなければ取引には応じませんよね。
そういったクライアントの不安や疑念を解消し、安心して取引を行ってもらうために、企業のブランド力というのは大きな要素となってきます。
ブランドといってもその定義は様々なため、本記事では言及しませんが、その要素の中には「社員の優秀さ」が間違いなく入っています。
取引先の社員が優秀であれば、不測の事態に陥った時でもしっかり対応してくれる、とクライアント側は安心できます。
企業側は学歴フィルターを設けて有名大学卒業者を多く採用することで、取引先であるクライアントに「有名大学卒業者が多い」=「優秀な社員が多い」という印象を与えることができ、引いてはクライアントからの信用獲得につながっていきます。
4. 企業文化・社風との相性を見るため
学歴フィルターを設けている企業では、当然社員の出身大学が限定されてきます。
そのことにより、社員の偏差値が近くなり、業務における知識レベルに大きな差が生じにくく、社内コミュニケーションが円滑に取れるようになるという傾向があります。
そのため、学歴フィルターを設けている企業は、さらに学歴フィルターにより自社に合うとされる学生を限られた範囲で探し続けることになる、ということが推察されます。
学歴フィルターのある企業の特徴
就活をしていて、「この企業は学歴フィルターを設けているのか?」と心配になったりすることは皆様もご経験があるかと思います。
ここでは、学歴フィルターを設けている企業の特徴をご紹介いたします。
下記に当てはまる企業が全て学歴フィルターを設けているわけではありませんが、少なからず学歴を基準に新卒採用の選考を進めている可能性が高いため、学歴フィルターを取り入れる理由をふくめて一つ一つ確認してみましょう。
有名な大手・老舗企業
知名度の高い大手企業や老舗企業は、就活においても学生から人気があり、応募が殺到する傾向にあります。
そのため、このような企業は採用活動において多くの学生に対処するべく、選考過程において一定の基準を設けて効率化を図る必要があります。
つまり、上述の学歴フィルターを取り入れる理由の一つ目である、「採用コストを削減する」ために学歴フィルターを取り入れている可能性が高いと推察できます。
また、「ブランド力の維持」という観点からも、有名大手・老舗企業は社会やクライアントに対するイメージ戦略の一つとして、高学歴の社員で固めることで一定の信頼を獲得している可能性が高いと考えられます。
給料が高い企業
社員の平均年収が高い企業も学歴フィルターが設けられている可能性が高いです。
理由として、給料が高いということは、社員はその給料に見合った仕事をするために高度な知識や一定の教養を持っている必要があり、企業側は給料分の仕事にしっかり責任を持ち成果を上げられそうな学生を採用する必要があるからです。
つまり、上述の学歴フィルターを取り入れる理由の二つ目である「基礎的な能力を担保する」ために学歴フィルターを取り入れている可能性が高いと推察できます。
具体的な業界や企業群として、総合商社、大手金融、保険会社、外資コンサルティングなどが挙げられます。
これらの企業は、選考時期も早く優秀な学生がこぞってエントリーするため、エントリーシートの時点で学歴フィルターにかけられてしまう可能性もあります。
本記事では、学歴フィルターを乗り越える方法もご紹介しているので、ぜひ最後まで読んでみてください。
また、給料が高い会社については下記コラムで詳しく解説しています。
ぜひ併せて読んでみてください。
”ビジ研!「【2025年度版】高収入の仕事に就きたい方必見!給料が高い仕事50選!」”
https://b-lab.tokyo.jp/columns/koushu-nyu/
リクルーターのいる企業
リクルーターとは、企業の採用担当者として、応募している学生に対して自社の説明を直接行ったり、面接対策を手伝ったりするなどのフォローアップをする役割を持つ者のことを指します。
リクルーターをつける目的として、企業に応募した優秀である可能性が高い学生を早めに確保することで、志望度を上げてもらい、内定を獲得してもらうことがあります。
さらに、リクルーターが存在する企業は、選考初期段階で期待値が高い学生をリストアップし、優先順位をつけてフォローアップしている可能性が高いです。
つまり、リクルーターをつけるかどうかや今後どれくらい力を入れてフォローアップしていくかという判断をする際に、学歴が大きな判断基準になっているという可能性があり、それが学歴フィルターとしてみなされています。
学歴フィルターを取り入れる企業のリスク

上記では、学歴フィルターを取り入れる理由や学歴フィルターを取り入れている可能性の高い企業について紹介してきました。
ここでは、そんな学歴フィルターを取り入れている企業が抱えるリスクについて解説します。
学歴フィルターは、学歴が高い学生には有利に働くことがありますが、しっかりそのリスクについて理解していないと入社後のミスマッチにもつながってきてしまいます。
ぜひ読んで参考にしてみてください。
1. 多様性に欠け、事業の不振につながりやすくなる
学歴フィルターを設定している企業では、採用対象が限られるため社員の出身大学や価値観、背景が似通った人材ばかり集まる傾向があります。表面的には社風がまとまりやすい一方で、同じ思考パターンの人材で集団が形成されるため、革新的なアイデアや視点が生まれにくくなる可能性が高いです。
市場変化への対応力が低下
現代のビジネスシーンは技術革新やグローバル化により、変化が非常に速いと言われています。多様なバックグラウンドを持つ社員がいれば、その分多角的なアイデアが生まれやすく、変化への適応力も高まります。しかし、学歴フィルターを導入している企業は同質的な人材が多いため、新しい発想を生む柔軟性が不足し、市場に取り残されるリスクがあります。
事業不振につながる理由
- イノベーションの欠如:似通った思考パターンでは革新的な商品・サービスを生み出しにくくなる可能性が高い
- 競合優位性の低下:多様な才能を取り入れにくいため、競合に先を越される可能性が高い
- 組織の硬直化:変化を嫌う社風が強まり、新規事業の立ち上げなどに消極的になりがち
2. 企業イメージの低下
近年はSDGs(持続可能な開発目標)やダイバーシティ推進の流れを受け、多様性を尊重する社会的価値観が広がっています。学歴フィルターを設ける企業は、そうした時代の流れに逆行していると見られがちです。
求職者から敬遠される可能性
企業の採用ページや口コミサイト、SNSなどで「特定大学しか採らない」「学歴が低い人は書類選考すら通らない」といった情報が広がると、求職者側は「この会社は学歴しか見ていないのでは?」とネガティブに捉えるようになります。結果として、企業ブランドやイメージが損なわれ、優秀な人材が応募を避ける要因になってしまいます。
消費者・取引先の評価にも影響
近年は採用の仕方ひとつで、その企業の姿勢や価値観が問われる時代です。SNS上での評判が瞬時に拡散される現代において、学歴フィルターの存在が明るみに出ると、消費者や取引先からのイメージダウンにつながる恐れもあります。
3. 企業の採用力の低下
学歴フィルターを設ければ、当然ながら応募してくる人材の範囲が限られます。特定の大学だけをターゲットにした場合、人材プール(母集団)の規模が格段に小さくなり、採用担当者が人材を見極める経験が少なくなってしまい、企業としての採用力の低下につながります。
優秀な人材を逃してしまう
学歴フィルターに引っかからない大学出身でも、優秀な人材は多数存在します。特にイノベーティブな思考や強い行動力を持つ学生は、必ずしも有名大学に在籍しているとは限りません。フィルターをかけることで、潜在的に優秀な学生を採用機会から外してしまうリスクがあります。
採用コストの増加
多様な大学からの応募が見込めない状態では、採用担当者がターゲット大学に繰り返し足を運ぶなど、限られた募集枠を確保するためにコストがかさむケースもあります。また、採用手法の幅も狭まり、企業全体の採用戦略が硬直化するデメリットも存在します。
4. 社内の派閥化
学歴フィルターによって同じ大学の出身者が多い企業では、学閥と呼ばれる派閥が形成されることがあります。学閥が強くなると社内人脈の偏りが生じ、新たに入社した人材が活躍しにくい環境になりかねません。
社員間の不公平感・モチベーション低下
特定の大学出身者が優遇されるような空気があると、他大学出身者や多様な経歴を持つ社員が活躍しづらくなります。結果として、社内の士気が下がり、モチベーションの低下や離職率の上昇につながる可能性があります。
組織の内向き志向
派閥が強い企業風土の中では、「社外の新しい知見を取り入れよう」という動きが弱まる傾向があります。これもまた、多様性を損ね、先述のような事業不振へとつながりやすい悪循環を生み出すのです。
学歴フィルターにかからない「学歴フィルター42校」とは
大学の中には、学歴フィルターにかかりにくく、比較的書類選考や面接選考などにおいて優遇されやすい大学が存在します。
一般的にそれら大学は「学歴フィルター42校」と総称され、学歴フィルターのボーダー基準として知られています。
下記にどういった大学が「学歴フィルター42校」に該当するのか、それらから求められる学歴フィルターのボーダーはどれくらいなのか、詳しく解説していきます。
学歴フィルター42校
以下に学歴フィルター42校をまとめた表を示します。
| 大学群 | 大学名 |
| 旧帝大 | 北海道大学、東北大学、東京大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、九州大学 |
| 関東国公立 | 一橋大学、東京工業大学、お茶の水女子大学、筑波大学、東京外語大学、東京医科歯科大学、東京農工大学、電気通信大学、首都大学東京、横浜国立大学、横浜市立大学、千葉大学、埼玉大学 |
| 関東私立 | 早稲田大学、慶應義塾大学、ICU(国際基督教大学)、上智大学、東京理科大学、学習院大学、明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学、芝浦工業大学 |
| 関西国公立 | 神戸大学、大阪府立大学、大阪市立大学、大阪外語大学(現在は大阪大学の一部)、奈良女子大学 |
| 関西私立 | 関西大学、関西学院大学、同志社大学、立命館大学 |
| その他 | 名古屋市立大学 |
これらの大学以外にも、学歴フィルターの影響を受けにくいとされる大学は存在するため、あくまで参考程度にとどめておきましょう。
学歴のボーダーラインは?
以下に学歴フィルター42校の偏差値をまとめた表を示します。
| 大学名 | 最低偏差値 |
| 東京大学、一橋大学 | 67.5 |
| 京都大学、東京工業大学、慶應義塾大学、国際基督教大学(ICU) | 65.0 |
| 横浜国立大学、早稲田大学 | 62.5 |
| 北海道大学、東北大学、名古屋大学、東京外語大学、神戸大学 | 60.0 |
| 大阪大学、筑波大学、お茶の水女子大学、電気通信大学、横浜市立大学、上智大学、法政大学、名古屋市立大学、大阪市立大学、同志社大学 | 57.5 |
| 九州大学、首都大学東京、学習院大学、明治大学、青山学院大学、中央大学、立教大学、大阪外国語大学、関西学院大学、立命館大学 | 55.0 |
| 東京医科歯科大学、千葉大学、芝浦工業大学、大阪府立大学、関西大学 | 52.5 |
| 埼玉大学、奈良女子大学 | 50.0 |
| 東京農工大学 | 47.5 |
| 東京理科大学 | 42.5 |
東京理科大学では、最低偏差値が42.5という数字がみられます。このように大学の内部において偏差値が低めの学部や学科も存在するため、学歴フィルターを乗り越えるボーダーとなる偏差値を一概に算出することはできません。
ただし、逆に考えると、偏差値が40代の方でも学部を絞って受験すれば学歴フィルター42校に入学し、学歴フィルターの網にかからずに就活を進められる可能性があります。
ただし、上記に該当する大学に在籍する学生さんでも、選考対策を怠れば容赦なしに落とされることは多々あります。現状にうぬぼれず、ひとつひとつ対策して就活を進めていきましょう。
転職でも学歴フィルターは存在するの?
本記事をご覧の就活生のなかで、「社会人になった後、転職するときにも学歴を見られてしまうのだろうか」といった不安を抱えている方も多いかと思います。
下記では、転職市場においても学歴フィルターは存在するのかについて詳しく解説しているので、ご参考にしてみてください。
転職では学歴はあまり重視されない
結論、転職市場では「学歴」よりも「実務経験や実績」が重視されます。
企業が求めているのは即戦力
転職市場と新卒採用を比較したとき、大きな違いの一つが“即戦力”の重要性です。新卒採用では、まだ社会人としての実務経験がないため、学生時代の取り組みや学歴をもとにポテンシャルを大きな判断材料として採用を決める企業が多いです。しかし、転職では“入社後すぐに成果を上げられるかどうか”が最大の評価ポイントになるため、過去の職歴やスキルセット、実績など、即戦力性を示す要素が圧倒的に重視されます。
学歴は「参考情報」にとどまる
もちろん、転職でも学歴をまったく見ないわけではありません。書類審査の段階で最終学歴をチェックする企業は存在します。しかし、そのウェイトは新卒採用に比べて格段に低いです。なぜなら、採用担当者は「大学名」よりも「これまでにどんな仕事をしてきたか」「どのような成果を上げてきたか」という実績を見て、採用を判断するからです。
転職で重視される点
逆に転職において企業が重視しているポイントとして、以下の3点が挙げられます。
・実務経験・職歴
・スキルセット
・成果を出すための「考え方」や「行動力」
以下に詳しく解説していきます。
1. 実務経験・職歴
転職で最も重要視されるのは、具体的な実務経験です。
たとえば営業職ならば「年間売上目標をどれだけ達成したか」「新規顧客の開拓実績がどれだけあったか」、ITエンジニアなら「どんなプロジェクトに携わり、どのような成果を上げたか」などが評価対象となります。
自分の持つ実績を数値化することによって、より説得力を増すことができます。
2. スキルセット
学歴よりも「今の仕事に活かせるスキル」をどれだけ持っているかが重要です。業務で使う専門的な知識や資格、あるいはプロジェクトを円滑に進めるコミュニケーション力やリーダーシップなど、企業が求めるスキルに合致しているかどうかが見られます。
3. 成果を出すための「考え方」や「行動力」
転職では、求める役割を果たせる人物を採用したいと企業は考えています。そのため、「問題点をどのように捉え、どう解決に導いたか」「チームとの連携をどう図ったか」などの仕事の進め方やコミュニケーションスキルも重要視されます。学歴ではなく、行動や考え方の一貫性から得られる信用が鍵を握るのです。
学歴フィルターの影響を受けにくい業界5選
上記で学歴フィルターの影響を受けにくい「学歴フィルター42校」について解説しましたが、「学歴フィルター42校に該当しない学生はどうしたらいいんだ」とさらに不安を抱えてしまった方もいるかと思います。
安心してください。新卒就活においても、学歴フィルターの影響を受けにくい業界・企業群は存在します。
下記で、新卒採用においても学歴をそれほど重視せず、どんな方にもチャンスが設けられている業界について詳しく解説していきます。
1. ベンチャー・スタートアップ
経営資源が限られるからこそ”結果”重視
ベンチャー・スタートアップ企業は、限られた資金や人材で急速に事業を拡大しようとする企業が多いです。そのため、学歴によるブランドや知名度よりも、「即戦力としてどのように貢献できるか」が重視される傾向があります。
具体的には、「実際の業務に役立つスキルを持っているか」や「チームへの貢献意欲や学習意欲」などが重視されます。
社員一人一人の裁量が大きい
ベンチャー・スタートアップ企業は、歴史が浅いことから組織体制が構築段階にあり、一人の社員が複数の業務を担うことが多いです。そのため、学歴よりも、「幅広い業務に積極的に取り組める柔軟性」が高く評価され、実力や成長意欲次第で内定を獲得することは十分可能です。
2. IT企業
スキルや実務経験が重視される技術職
IT業界では、プログラミングスキルや設計・開発の経験など、技術的なスキルが即戦力として認められるケースが多いです。大学名や選考よりも、どのプログラミング言語が使えるか、どんなシステムを作った経験があるのかなどが評価基準となるため、学歴フィルターの影響はかかりにくいです。
新たな技術を追いかける文化
IT企業はテクノロジーの進化が早く、新しいサービスや技術を常に取り入れなければ競争に勝てません。そのため、技術職にかかわらず、営業や企画職においても学習意欲や好奇心、最新の技術トレンドをキャッチアップできる柔軟性が求められます。学歴よりも実務でのアウトプットやポートフォリオなどが重視されやすいのが特徴です。
3. 外資系企業
グローバルな評価基準と結果重視の風土
外資系企業は、本社が海外にあるため評価基準がグローバルスタンダードに近いものとなっています。新卒採用においても、「英語力」「コミュニケーション能力」「論理的思考力」など、結果につながりやすいスキルやポテンシャルを重要視することが多く、大学名や専攻といった学歴などをそれほど重視しないケースが多くみられます。
個人のパフォーマンスによって評価される
外資系企業は成果主義の文化を持つことが多く、個人の目標達成度合いが評価の中心となってきます。入社後においても、成果を上げた社員に関しては、学歴に関係なく昇進・昇給のチャンスが与えられます。
4. エンタメ・クリエイティブ系業界
”作品”や”企画力”が評価の決め手
エンタメ・クリエイティブ系では、学歴よりも作品・企画・実績が採用判断の主軸になります。例えばデザイン・映像制作・ゲーム開発など、政策実績やポートフォリオなどアイデアの独創性が採用のカギとなります。
個性と発想力を重視する風土
エンタメ・クリエイティブ系企業は多様な人材が集まる業界です。作品やアイデアを発想できる力やトレンドへの感度の高さが重視されるため、学歴での足切りが起こりにくい特徴があります。
5. 接客・サービス業界
現場での”対応力”が重要
接客・サービス業界(ホテル、飲食、アパレル、旅行業界など)では、何よりもお客様に対するホスピタリティやコミュニケーション力が重要視されます。学歴よりも「人と接するのが好き」「場を盛り上げるのが得意」といった人柄や柔軟性が採用の決め手になることが多い傾向があります。
キャリアアップの早い企業も多数
接客・サービス業界では、若いうちから店舗のマネジメントを任される機会も少なくありません。学歴に関係なく、実績やリーダーシップが認められれば早い段階で昇格できる可能性があります。
学歴フィルターを乗り越えるコツ

上記では、学歴フィルターの影響を受けにくい業界について解説してきました。
しかし、実際に自分がどうしても行きたい企業に学歴フィルターが設けられていそう、といった状況に面したときどうしたらいいのでしょうか。
下記では、そういった学歴フィルターを乗り越えようと強い意志を持った方向けに、学歴フィルターを乗り越えるためのコツを詳しく解説していきます。
ぜひ最後まで読んで、逆境に負けず精いっぱい努力する糧にしてください。
学歴以外の実績を作る
学歴以外で評価される要素を作ることは、企業の選考で有利に働きます。つまり、「学業以外で力を入れた項目」いわゆる「ガクチカ」を培うことが有効打となります。
たとえば、大学のゼミ活動、サークルでのリーダー経験、ボランティアや留学経験などが挙げられます。学外の活動だけでなく、趣味や特技を深めて成果を残すことも大切です。「何をどれだけ頑張ったか」「どんな困難をどう乗り越えたか」を具体的に語れるエピソードが、企業側の興味を引くポイントになります。
<学歴以外の実績を作る方法>
・学外イベントやコンテストに参加する
大学内外で実施されているビジネスコンテストやアイデアソンなどに積極的に参加することで、学業では培われない視線や人脈を形成することができます。そこでの受賞歴やプレゼン経験は企業へのアピール材料として有効です。
・成果を数値化する
アルバイトでの売上アップ率やチーム活動での目標達成率など、自分の行動により目標に対してどれだけ貢献できたのかを数値化することにより、説得力を増すことができます。
・主体的に企画・運営したエピソードを準備する
学生団体やサークルなどのイベント運営など、組織を動かす経験はリーダーシップや主体性のアピールにつながります。特に、自分の力で周囲を巻き込んで成果を出した経験は、どんな環境でも再現性が高いため、面接でも好印象を得られやすいでしょう。
選考対策を徹底する
いくら学歴が高くても、面接や筆記試験の対策が不十分だと選考突破は難しいものになります。
逆に、学歴フィルターに届かない学歴だとしても、選考対策を十分に行うことによって、選考を突破し内定を掴み取ることができます。
具体的には、過去の経験や性格を整理し、「自分はどんな人間か」「なにを大切にしているか」を言語化したり、模擬面接を繰り返し行うことで、質問に対する回答をブラッシュアップすることなどが挙げられます。
<選考対策の方法>
・自己分析を徹底する
自己分析が不十分だと、採用担当者の「この学生の強みはなんだろう?」という疑問に答えることができないまま選考が進んでしまいます。自分の強みや弱み、価値観、将来像などを徹底的に整理し誰にでも伝わるように言語化することで、自分をアピールしていきましょう。
・面接練習を積む
具体的には、友人やキャリアセンターでの模擬面接を何度も繰り返したり、その様子を録画し客観的にチェックすることも重要です。企業によっては、対話型の面接であったりプレゼン型の面接であったり、面接の雰囲気はさまざまであるため、自分の志望する企業にあわせて対策していきましょう。
・企業研究を徹底する
企業の特徴や求める人物像を理解しないまま面接に臨むと、漠然とした受け答えになりがちです。上場企業であればIR情報、非上場でも公式サイトや業界ニュースを細かくチェックして、面接時に具体的な質問・提案ができるよう備えましょう。
インターンに参加して活躍する
インターンシップでは、新規事業企画や既存事業の利率アップの施策提案など、実際の実務に近い活動を通じて活躍する姿を企業側に直接見せられるため、そこでの評価は学歴ではほとんど左右されません。また、早期からインターンシップに積極的に参加すれば、内定直結型の選考につながることもあります。
<インターンシップに参加して活躍する方法>
・長期インターンシップに参加する
1日〜数日間の短期インターンに比べ、長期インターンは実際に事業に携わり営業やマーケティング活動を行います。成果を出すチャンスが多いため、職務経歴に近い実績を作れる点がメリットです。
・企業への熱意を行動で示す
インターン中は「何でもやります」という姿勢だけでなく、主体的に課題を見つけて提案・実行することが評価につながります。そのような評価は学歴に依存しないため、提案型の思考やコミュニケーション力で十分アピール可能です。
・実績をまとめる
インターンでの具体的なプロジェクト内容や学んだことは、面接やESで書くネタとして非常に強力です。数値的な目標や自分の揚げた成果を明確にし、わかりやすくまとめておきましょう。
専門性の高いスキル・資格を身に着ける
簿記やTOEIC、ITパスポートなどは幅広い企業で評価を得やすい資格です。また、マーケティングやデータ分析に関する知識を独学で身に着けることで、就活において大きなアドバンテージを得ることができます。専門性を証明できる資格やスキルは、学歴以外の客観的な評価材料になるためおすすめな施策です。
<専門性の高い知識・スキルを身に着ける方法>
・興味のある業界・職種を調べ、必要な資格を選ぶ
例えば、金融業界であれば簿記、IT業界であればITパスポートなど業界に関連する資格を知り、勉強していきましょう。
・計画的に勉強する
資格とはその分野に対して一定の知識やスキルを所持していることを公式に認定するための証明書です。その取得のためには見合った勉強時間が必要となってきます。普段の学業とうまく折り合いをつけ、休日や隙間時間を有効活用し、地道に勉強を進めていきましょう。
・学んだ内容をアピールにつなげる
単に資格取得で終わらせず、学んだ知識をどうビジネスに活かせるかを具体的に話せるように準備することが大切です。
知名度の低い企業にも注目する
就活ではどうしても有名企業や大手企業に人気が集中しがちですが、優良企業は大手だけではありません。いわゆる「隠れ優良企業」に目を向けることで、学歴フィルターを感じにくい選考を受けられるチャンスがあります。業界のシェア率や経営状態、従業員満足度などを調べてみましょう。
<知名度の低い企業に注目する方法>
・中小・ベンチャー企業をリサーチする
就活サイトやSNSだけでなく、業界新聞・経済誌などからも情報を収集し、注目の新興企業や独自技術を持つ中小企業を探してみましょう。成長企業であれば、早期のキャリアアップも期待できます。
・企業の成長性や社風を重視する
大企業よりも一人ひとりの業務範囲が広く、早い段階から実力を積めるケースがあります。将来的な市場性や自分との相性を基準に企業を選ぶことで、長期的に活躍しやすくなります。
・経営者や社員の声を調べる
ベンチャー企業は特にSNSやブログなどで経営者や社員の発信が活発です。そこでの情報をもとに志望動機を強化し、面接時に具体的な理由を伝えられるように備えましょう。
OB/OG訪問する
OB/OG訪問は、自分の大学出身者だけを頼るイメージが強いかもしれませんが、SNSや就活支援サービスを利用すれば、学歴や大学を問わず多くの社会人とつながれます。現場で働く先輩の話はリアルであり、企業の内情を知る絶好の機会です。
また、面接の場でも、企業の情報をホームページやSNSだけで得ている学生よりも、OB/OG訪問を実施し生の声を得る活動をしている学生のほうが志望度が高く行動力のある就活生であると評価されるため、OB/OG訪問の実績は積極的にアピールしましょう。
<OB/OG訪問する方法>
・SNSやビジネス系プラットフォームを活用
X(旧Twitter)やLinkedInなどで働きたい企業や業界の社員をフォローし、直接メッセージを送ってみるのも一つの手です。就活生向けに受け入れてくれる方も多いため、積極的にコンタクトをとりましょう。
・事前準備をしっかり行う
OB/OG訪問では、事前に知りたいことや企業研究の結果をまとめておくと会話がスムーズです。短い時間を有効に使い、自分の強みをどう活かせるかなど具体的な質問を用意しておくと良いでしょう。
・フィードバックを面接対策に活かす
先輩から聞いた内容は、面接の志望動機や自己PRを補強する材料になります。自分が企業でどう働きたいか、その具体像を形成するうえでリアルな視点を得られるメリットは大きいです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。本記事では、学歴フィルターについてその実態と、どんな企業が学歴フィルターを設けているのか、学歴フィルターを乗り越えることなど多岐にわたって解説してきました。
結論として、学歴フィルターの影響を受ける方もそうでない方も、最終的にはしっかりと選考対策をして、どれだけ自分をアピールできるかが内定獲得を左右します。
現状に甘えず、現状を悲観せず、一歩一歩着実に準備を進めていきましょう。
本記事が皆様のよりよい就職活動の一助になったら幸いです。

 お問合せはこちら
お問合せはこちら